川島健『ベケットのアイルランド』 [本]
本は、ぽつぽつ読むには読んでいるが、なかなか面白いと感じられるものに出会わない。
本との相性もある(たとえば求めている方向が同じで前を歩いているか、逆に、方向は違うが気づかされることがことがあるか)。また、本はいいのかも知れないが、自分の受け取る力が不足していて感じ取れないことに問題があるかもしれない。時がたてば、その本を再度受け取れることがあるのかな?
川島健『ベケットのアイルランド』は、目を開かれるような面白い本でした。
私の理解が正しいのか判りませんが、気になった事柄を記します。
序章で、「本書の目的はベケットのテクストを、アイルランドをめぐる様々な言説のなかに位置づけ分析することである。…ベケットの軌跡と…アイルランドの歴史を交錯させ…ベケットのアイルランドの相貌の変化を写しとり、現実のアイルランドの変化に重ねあわせることが本書の方法である。」(P14)としています。
イェイツによる(アイルランド)民族主義批判をとりあげて、イングランドとアイルランドの「中心/周辺という二項対立はもはや崩壊し、周辺同士が連結、離反しながら新たな地政学を作り上げる時代となったのだ。」(P24)
次にベケットのエッセイ「最近のアイルランドの詩」(1934年)を読み解き、そのなかの「無人地帯、ヘレンポントス、真空地帯」という言葉をキーとして、見て取ろうということです。ヘレンポントスは、ダーダネルス海峡(トルコ)の古名で、エーゲ海とマルマラ海の境界に位置し、紀元前三二二年のディアドコイ戦争の舞台といいます。
「…「無人地帯」はそもそも軍事用語で「緩衝地帯」を意味し、対峙する軍隊のどちらの支配下にも属さない地域を意味する。…ベケットがここで強調するのは、…「無人地帯」は所有権の確定していない場所、誰のものでもなく、またそれゆえ、誰のものでもなりえる空間を名指すための言葉である。
ベケットは一九三〇年代のアイルランドを「無人地帯」とみていた。実際に、イギリスからの独立へと向かうその国は決して一枚岩のように団結していたわけではない。…様々な主義主張に引っ張られ、刻まれ、歪められ開いた裂開をベケットは「無人地帯」とよんだのだ。・・・
ベケットの描くアイルランドを読み解くために、本書は「無人地帯」を拡大解釈し、・・・ベケットが残したテクストを分析するための鍵語とする。」(P27)
著者の問題意識を明確するため、長く引用しました。この“無人地帯”の名指しについて、私自身は未消化なところがあります。一つは、アーレントの“アゴラ”ような公共性を持つ討議広場(空間)、誰のものでもなく、誰のものともならない空間として(懐古的に?)考えるべきか、あるいは単に無秩序で混乱していて、未確定で油断もすきもなく、ボーッとしていたら誰かの物(所有)になってしまう、(ウクライナ・クリミヤ半島や日本にもあるように)現実の“囲い込み”“実効支配”を争闘する“名指すべき”地帯なのか。“境界”では、本当に、潜勢的可能態という状態が“牧歌的に”開かれたまま滞留しえるのか?様々な利害が衝突している時、その対立構造を拒める(バートルビー的)倫理の立場がその“境界内”に成立するのだろうか?“無人地帯”とは、入れ子になって空けられた有人地帯に過ぎないのではないか?・・・など、考えを呼び覚まされるほどの提案だ、と言っておきましょう。
著者は、章ごとに魅力的なテーマを縦横に論じています。いろんなテーマがあるので深追いせずサラッと記すことにしておきます。
ダンテの『俗語詩論』(1305?)を題材に、ウンベルト・エーコやジョルジョ・アガンベンを踏まえ、
「・・・ダンテは、「俗語」を神学(完全言語)や政治(普遍言語)から解放する。」(P86)
T・S・エリオットの検討では、
「・・・その修辞の曖昧さにこそ彼の政治的な意図が込められている」(P89)
「詩人と言葉の関係を論じるこの文章では、…詩人と言葉の互酬的関係は共同体意識を強化する。…詩人の役割とは言葉を通して人々の感性を高めることにある。主人的態度が詩人と言語の一対一関係を前提とするのにたいして、召使的態度は、言語を通して多くの人々の感性教育に益することを目的とするため、一対多の関係を目ざす。…エリオットは「共通言語」の重要性を訴え、詩と日常言語の有機的関係を強調するのだ」(P93)
「…エリオットの共通言語への希求は言語を資源とする考えに基づく。」(P95)
「…ベケットはダンテを読むことにおいて、芸術と日常、テクストと現実を切り離すことが必要であることを強調する。」(P97)
「「高貴な俗語」が文学形式であることを明記するベケットは、社会に還元されぬ余剰性こそがダンテの言語的特徴であり、そのような言葉こそ文学にふさわしいと考えた。ヴァーチャルな時空にしか存在しないのであれば、その言葉は発生の起源を歴史的に求めることはできない。それは神の言葉(完全言語)の喪失を代補するものだが、神の言葉を再現するものではない。…ダンテの俗語は「完全言語」という起源への遡及を封じたところで創り出されたものだ。言葉の起源を遡及的に探し出そうとし、その帰属を求める探求にたいする疑義をベケットはダンテから引き継いでいる。」(P101)
「ベケットが「ダンテ・・・ブルーノ・ヴィーコ・ジョイス」の冒頭で敷衍するヴィーコの言語論がここでは重要だ。『新しい学』(一七二五)でヴィーコは、詩人は人類の感覚であり、哲学者がそれを理性的に解釈するという。その詩的言語の要点は、国家に芸術が従属するという考えを転覆し、詩と物語こそが国家の起源だという主張にある。…その言葉は公式の言葉(普遍語)ではなく、詩的な言語でなければならない。」(PP108-109)
なるほど人類最古であろう、リグ・ヴェーダ賛歌があってウパニシャッドが生まれるのであって、逆ではない。その後の言葉の発展と精緻化や公定語の確立において、プラトンの『詩人追放論』(オウィディウスやマヤコフスキーの、あまたの詩人の亡命や死)を含め、国家は何を求めるものかを示すものでしょう。もし詩が《歴史的に》国家の起源(目的化)となるなら、(残念ながら転倒して)実現した国家は《論理的に》詩を源泉(道具化)にする、という神話化と世俗化の関係が両立すると思います。肝心なのは、古代・古典の真相というよりも、誰が実利を引き出してきたか/しまうのか?でしょう。
これ以降も、翻訳についてや、名付けについては“スタインの言語”とか“唯名論的詩論”、廃墟論では社会構築主義と本質主義との対立についてなど、興味深く玉手箱のような話題を取り上げてくれています。刺激的でどれも面白い。体がしんどくて書き切れないので、何かの話題で、この本に立ち返ることにしたいと思います。こうしたテーマを、まさかボルヘス風に書かないでしょうし、下記のオーデンのようにも書かないとすれば、この著者川島氏の本として書かれ、読まれなくてはならないでしょう。
さて、ヘミングウェイの『移動祝祭日』で、パリのレストランでジョイス一家はいつもイタリア語で語り合っていたことのわけや、ベケットがフランス語で書いたことについて、菅啓次郎が「語学者ベケット」で、「ベケット家はもともとフランスから逃れてきたユグノーの家系だったから、フランス語に戻ることは先祖の言葉に戻ることだった。」という一つのエピソード紹介し、<母語>と<外国語>の問題、多和田葉子の<エクソフォニー>を振り返る機会ともなっています。
この本で感じたことは、支配文化と民衆文化としてのイギリスとアイルランドの関係理解に、ベケットがどう切り開く可能性を持ちえているか、つまり従属する現実を解決する出口を見出せるか(二項対立のダブルバインド、ポストコロニアルの論議、読者の共感や連帯のテーマも論じています)ということなのか。または文芸批評としてのベケット文学が示す地平線をアイルランド方角で照らしただけ、ということなのか、著者川島氏の視点立場がもうひとつ飲み込めなかった。これが、著者のいう“無人地帯”なのかもしれないが…。
それから、ヘミングウェイでよく知られている《ロスト・ジェネレーション》(第一次大戦後の迷える、自堕落な世代)に対して、この本で《オーデン・ジェネレーション》(P83)というものも知りました。それは、スペイン内戦に参加していく知識人、A・マルロー、ヘミングウェイ、G・オーウェルらの動向、「詩がもはや机に向かって書くものではなく、行為とともにあり、ある種の決意表明となった時代だ。」(P83)というものです。
機会があれば、著者の文章をまた読みたいという印象が残りました。
最後に、本カバーのスケッチが、ジャック・B・イェイツのもので、「オコンネル橋かにみたダブリン、1916年5月12日」でイースター蜂起後の首謀者の処刑日のことで、オコンネル・ストリートのネルソン記念塔とダブリン中央郵便局を描いたもので、思い入れを感じ、グッとくる。
著者の「あとがき」にある、
「本の頁を照らすのは仄暗い情熱であるべきだ」(P257)
まるでゲーテの『ファウスト』に書かれているかのような言葉、詩人だなぁ、と感心しました。
骨転移、まだ続く癌との戦い [ガン闘病記]
術後三ヶ月も経過し、さて九月から職場復帰しようと心構えと準備をしていた。
しかし、八月のCT検査の結果で、背骨への骨転移がわかった。背中の鈍痛が、術後の痛みを過敏に感じているのかと言われもし、そうなのかと思っていたら、癌の骨転移が原因でした。
骨が溶けて脊髄まで到達すると下肢の麻痺や排尿障害が起こるとのことで、取り急ぎ、骨病変の進行をとめるため“ゾメタ”という薬を静脈点滴うけました。鎮痛剤もMSコンチン錠(10mg)からリリカカプセル(75mg)に呼吸器外科が切り替えようとしていたが、検査結果により、MSコンチン錠(10mg) プラス ロキソニン錠(60mg) それと胃を守るためのパリエット錠と、薬が増えてしまいました。
九月の中旬から放射線治療を2週間続けることなり、職場復帰は当面お預けです。たしかに背中の鈍痛で、本当に仕事が出来るだろうかと自問自答していたので、状態からすれば当然かなと思う出来事です。ただし、心理的なガッカリ度は大きくて、先の不安感で夜はなかなか寝付けない。
窓から見える、大好きな夏の青い空と白い入道雲が切ない。
栃木・壬生、バンダイ・ミュージアム [ガン闘病記]
癌になってから、離れて住む息子が孫と過ごす時間を意識して作ってくれる。
今年の夏は、天候があいにくになってしまい、栃木の壬生にあるバンダイ・ミュージアムという屋内施設の見学ということになった。あまり大きくない施設で、正直ぱっとしない感じでした。
古いオモチャが展示されているのだが、そのオモチャをみて自分の子供の頃を思い出してしまった。
私は幼い頃は、関西に住んでいて、よく父に連れられ大阪に出たものだった。(後年、姻戚のおじがいて訪ねていたということがわかった)
百貨店に行ってオモチャ売り場のオモチャがよく記憶に残っている。
列車で大阪に出ていたこともあり、鉄製のレールを走るゼンマイ仕掛けの機関車を何度か買ってもらった記憶がある。この機関車は、バンダイ・ミュージアムでは見かけなかった。
しかし、大変思い出深いオモチャを二つ見つけた。 一つは、ブリキ製だったが、たしか内臓電池で動き、障害物があると方向を変え自由に動き回るものだった。動きが面白くて、父に買ってもらった記憶がある。
一つは、ブリキ製だったが、たしか内臓電池で動き、障害物があると方向を変え自由に動き回るものだった。動きが面白くて、父に買ってもらった記憶がある。
 もう一つは、ロボット。これは映画で見たものだったので興味があったが、(映画同様)動きが緩慢だったので、迷ったが、上記のジグザクに動く円盤にした記憶がある。
もう一つは、ロボット。これは映画で見たものだったので興味があったが、(映画同様)動きが緩慢だったので、迷ったが、上記のジグザクに動く円盤にした記憶がある。
この映画が何だったのか、ずいぶん記憶もなかったのだが、2003年にスーパー・ハリウッド・シリーズでSF映画の古典『禁断の惑星』(1956年)というジャケットを見て購入し、映画を見て内容を思い出した。“イドの怪物”というどんなに知能が発達して高度な文明を誇ったとしても、発達の過程で持っている原始的な衝動欲求が消えることなく支配している。それがために、高度な宇宙人の文明が滅び、人間がそこに到達しようとしても、やはり“イドの怪物”によって殺人や破壊が繰り返されてしまう、という内容。
出てくる問題のロボットは“ロビー”といって、『スター・ウォーズ』のR2D2にも影響を与えた、とDVDのジャケット紹介がされている。
私には懐かしい時間だったが、息子は息子なりに、孫は孫なりに楽しめたろうか?
アルベルト・マングェル『読書礼賛』(3) [本]
さて、第6章の本をめぐるビジネスでは、翻訳についての文章が収められている。しかし、もっとも興味をもったのは「ヨナと鯨」という文章です。ヨナは旧約聖書の預言者で、旧約聖書の知識がなくても、ヨナ書が簡略されて紹介されています。とりわけ政治と芸術という関係で面白く読めました。
「芸術家には死後の名声だけで十分なのだ」(P326)
「プラトンにとって、そもそも真の芸術とは政治家だった。正義と美という神聖なモデルにそって国家を築く人びとである。一方で、作家や画家といったふつうの芸術家は、そのような価値のある現実について思いめぐらすことをせず、たんに幻想を紡ぎだすだけであり、それは若者の教育にそぐわなかった。芸術は国家に奉仕するときだけ有用だとするこうした考え方は、何代にもわたるさまざまな政府に支持されてきた。皇帝アウグストゥスが詩人のオウィディウスを追放したのは、この詩人の書くものに潜む危険性を察知したからである。」(P331)
以前に、『マヤコフスキー事件』の運命について書いたこととつながる話です。
マングェルは、フローベールの『紋切型辞典』をひいて、芸術家に対する19世紀ブルジョアの考え方として、「芸術家―すべてが道化師。無私無欲な態度が賞賛される。ふつうの人と同じような服装をしていることが意外に思われる。たくさん稼いでも、残らず使い果たす。」(P332)を引用しています。身持ちの悪さ、放蕩、蕩尽、破天荒さ、普通と(どれほど)異なっているかが、高度な?芸術性をあらわすのでしょう。「すべてが道化師」とは、さすがはフローベール。
「芸術家に対する彼らの態度をあらわす言葉は、第二次大戦中にユダヤ人移民の受け入れに対処したカナダ移民局の役人が口にした言葉「ゼロでも多すぎる」と同じだ。」(P332)
「ドードー鳥の伝説」(PP355-356)というモーリタニアの言い伝えは、短い寓話ながら面白い。
第7章罪と罰。「読書から学べるとおり、人間の歴史は不正のはびこる長い夜の物語である。」(P348)という文から始まる「神のスパイ」(1999年)は、大変印象深いルポルタージュになっています。マングェルが学生時代に知り合った女子下級生の話。1969年にブエノスアイレスを離れ、1982年に短期滞在で戻ってみたら、学生自治委員会のメンバーだった彼女は誘拐され行方不明になっていた。今回のワールドカップでもお馴染みの、アルゼンチンの軍事独裁政権下の出来事です。
1976~78年の時期に軍による処刑として、看守であった曹長ビクトル・アルマンド・イバニェスのインタビューを紹介しています。
「囚人たちはパナノバルという強力な薬を注射され、数秒間で息絶えた。その薬は心臓発作のような症状を起こした。それから、彼らは海に投げ込まれた。飛行機は高度を下げて飛んだ。それは隠密飛行で、記録には残されなかった。ときたま、鮫のような巨大な魚影が飛行機のあとを追ってくるのが見えた。奴らは人肉で肥えているとパイロットがいった。」(P351)

地を這うように―長倉洋海全写真1980‐95 (フォト・ミュゼ)
- 作者: 長倉 洋海
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1996/06
- メディア: 単行本
私は、この話を読んで、『地を這うように―長倉洋海全写真集1985-95』のエル・サルバドルでの「内戦の中米へ」に収められた、女性を殺害して野ざらしになった一葉の写真(著作権があるから写真を出すわけにはいきません)が浮かびました。何があったのか、恐ろしい情景となって迫るものがあります。
こうした時代の評価を巡り、バルガス=リョサの問題記事、ファン・ホセ・サエールの反論、フリオ・コルタサルの見解を載せています。関連して、『疎外と叛逆―ガルシア・マルケスとバルガス・ジョサの対話』、『抵抗と亡命のスペイン語作家たち』も面白かったですよ。
「記憶のおかげで、自分という存在、そして自分が見るものに意味が与えられる。」(P365)
第8章荘厳なる図書館から「理想の図書館とは」
「理想の図書館の入り口には、ラブレーの金言をもじった「汝の欲するままに読め」という言葉が掲げられている。」(P387)
「理想の図書館は、つねに更新される終わりのないアンソロジーである。」(P389)
次の「さまよえるユダヤ人の図書館」から
「国を持たない放浪者と都市居住者、遊牧民と農民、探検家と家庭を守る者…は、あらゆる時代において、この二つの憧れを体現してきた。片方は外に向かい、もう一方は内に留まろうとする。…人を駆り立てるこの二つの力は競い合うと同時に補完しあう。自分の故郷と呼ぶ場所から遠く離れることで、人は自分の真のアイデンティティを感じられる。だが同時に、自分の内面を深く見つめることから気を逸らされることも多い。…」(P397)
「やがて、日常生活と夜の物語の違いに気づくと…本のおかげで、言葉が日常生活に意味を与え、夜の物語を理解できるものにし、そして昼と夜の両方にいくらかの慰めを添えてくれているのだ、と。」(P398)
「…敵をやっつけ、みずからを守りたいという思いが強いあまり、私たちは安全であるとはどういうことかを忘れてしまう。あまりにも大きな不安のなかで、自分たちの権利と自由が歪められ、あるいは切り詰められるのを許してしまう。外にいる他者と対峙するかわりに、私たちは内に閉じこもってしまう。自分たちの図書館が世界に開かれるべきものであり、世界から孤立するふりをしてはいけないということを忘れてしまっている。私たちは自分自身の虜囚になっているのだ。」(P401)
「永遠にさまようことは罰なのか、それとも世界を知ろうとする啓蒙的な行為なのか。居心地のいい自分だけの場所は報償なのか、それとも忌むべき沈黙の墓場なのか。「他者」とは名前のない敵か、それとも自分自身の投影なのか。私たちは一個の孤立した存在なのか、それとも時間を超え、世界を意識した多くの存在の一部なのか。」(P402)
マングェルは、六十年余の遍歴生活で集めた三万冊ばかりの蔵書を持って、フランス、ロワール渓谷の南の小さな村に住むという。二〇〇八年には緊急手術に迫られ、「人生のあるとき、私たちはたくさんの本のなかから、なぜその一冊の本を伴侶として選び出すのだろう?」(P414)と、私がガン手術受けたときのように、迷ったようです。私は(七千冊余から)結局選べなかったのですが、マングェルは「結局私が頼んだのは『ドン・キホーテ』の二巻本だった。」といいます。私なりに得心のいく選択のような気がします。
さて、「訳者あとがき」に書かれているように、ブエノスアイレスに生まれ、イスラエル駐在大使の息子としてテルアビブで幼少期を過ごし、小学生でアルゼンチンにもどり、ユダヤ人である人種アイデンティティに気づく。高校生になると、先住民の貧困を目にして社会の暗部を垣間見るが、チェ・ゲバラのように革命に身を投じることは出来なかった。そのころボルヘスをはじめとする作家たちと知り合ったという。アルゼンチンの軍事政権が権力掌握した時代、大学を一年で中退して、ヨーロッパで放浪生活を送る。
「そのままアルゼンチンにとどまったら、友人たちの多くと同じように、軍事政権に与するか、あるいは抵抗運動に身を投じるかの選択を迫られ、後者を選んだ場合は逮捕、拷問、行方不明という運命を辿っていたかもしれない。故国を捨て、家族や友人たちの苦境から距離をおかざるをえない亡命生活は苦渋の選択だったはずである。」(P427)
私にとって、マングェルの半生のメモリアルが、なんとも熱く胸に迫るものが感じられる。重みのある一冊だと思います。
アルベルト・マングェル『読書礼賛』(2) [本]
まず初めに、今回は、後半としてまとめられず<中>ということになりました。
「ロシアの作家イサーク・バーベリは書いている。「完全に結末をつけようとするあの力をまさに正確な場所に用いなければ鉄といえども心臓を刺しつらぬくことはできない」。言葉の強力さと無力さの両方を知る者にとって、この信頼に足る最後の小さな点ほど役に立ってくれるものはほかにない。」(P177)
「カン・グランデ・デッラ・スカラにあてた有名な書簡で、ダンテは読書について語っているが、…読書の分類、または段階的な読書(逐語的、寓意的、類推的、神秘的)についての議論がなされるが・・・」(P201)
「セルバンテスと同じように、私たちは自分の運命をほとんど見きわめることができない。意識に縛られた私たちは、生きることが旅に似ていると理解している。すべての旅がそうであるように、人生には始まりがあり、いつかまちいがなく終わりが来る。だが、いつ最初の一歩が始まり、その歩みがいつまで続くのか、この旅でどこに向かうのか、その理由は何か、どんな結果が待っているのか、これらの問いかけには、非情にもけっして答えが得られない。ドン・キホーテその人と同じように、私たちは自分を慰めることができる。自分の善意と高貴な苦しみがいつかきっと不可思議なめぐりあわせで自分の人生を正当化してくれるに違いない、課せられた役割を果たすことで自分はひそかにこの宇宙を支えているのだと信じることによって。」(P207)
「セイレーンが登場する『国家』の同じ巻で、プラトンはすでに世を去った古代の英雄たちに、生まれ変われるとしたらどんな一生を送りたいか語らせている。オデュッセウスの魂は、前世で野心ためにどれほど苦労したかを思い起こし、他の魂が軽視して捨て去った、ごく平凡な市民として生涯を送りたいという。…それと引き換えに欲したのは、無名人としての静かな暮らしだった。」(P219)
人は死んで名を残す。英雄の時代は死の最後の瞬間までおだやかな時間を与えないだろうと思う。日常を捨て非日常を選び取ることは、安らぎを捨て去って、激動を突き進むことなのだろう。マングェルが『チェ・ゲバラの死』を書いたことも伏線はこれだろう。「毛(沢東)の盟友彭徳懐は北京の西郊の農村で労働と読書の日々を送っていたが、「六六年暮、江青、林彪の意を受けた紅衛兵によって北京に連れ戻され、繰り返し批闘(批判・闘争)大会で残酷な暴行を受けた末、病院に幽閉され」「監禁されたまま七四年十一月、七十六歳で死去」した。」大池文雄『水戸コミュニストの系譜』(P344)。外なる世界での少しばかりの冒険と内なる世界のっぺりとした平凡な私生活を、混合して個人の都合で生きることは出来ないという教訓かな。
「市民の反抗精神をそそのかすという理由で『ドン・キホーテ』を禁書にしたピノチェト…」(P228)
『ドン・キホーテ』については、木村榮一『ラテンアメリカ十大小説』(岩波新書)でも、「(ラテンアメリカの)植民地時代は、セルバンテスの『ドン・キホーテ』を所有しているだけで異端審問にかけられるほど厳しい検閲制度が敷かれていました。」(P7)とこの本の特異な性格を伝えています。今思えば、私も中学時代に読んで、あまりの面白さに、いつかもう一度読もう、と心に誓った唯一の本であったことを思い出します。
「「少なく考え、たくさん働け」というのが、二〇〇七年七月二十一日、当時ニコラ・サルコジ政権の財務担当相だったクリスティーヌ・ラガルドが発したメッセージ」(P241)
「パラドックスや未解決の難問、矛盾や混沌とした秩序について深く考えることの困難に直面した私たちは、ローマ元老院の大カトーの叫び、「カルタゴは滅ぼされるべきである!」を思い起こさずにはいられない。すなわち、他の文明は受け入れがたく、話し合いなど拒否して当然、追放と滅亡によって法律を順守させるべきである、というのだ。」(P242)
同じ逸話はまだあって、紀元前三世紀、ギリシア時代のシチリアで、攻め込んだローマの将軍はアルキメデスを殺さず生け捕りにしたかったが、一人のローマ兵が七十五歳になっていたアルキメデスを連行しようとしたとき、「そこに立って私の図形を乱さないでくれ」といい、それに激昂してアルキメデスを剣で殺害した。そうしてローマは三千年のギリシア文明(様々な発明、アンティキテラなどもありました)を引き継がず、途絶えてしまう。再び、アラビアからギリシャ文明を再発見する十二世紀のルネサンスの目覚めまで、一五〇〇年近く惰眠してしまう。
マングェルは、ナチによるホロコーストに先立って、トルコ政府によって「…最も古い歴史のあったアナトリア地方の全住民、子供を含めた男女およそ百五十万人以上が一九〇九年から一九一八年のあいだに皆殺しにされた。」(P158)と、第3章覚書で記していました。
「人が最初に抱く強い感情は、自分の周囲にあるものを解読したいという欲求だ。あたかも森羅万象に意味があるかのように。意味を伝えるための記号体系―アルファベット、象形文字、絵文字、社交のための身振り―だけでなく、人は身のまわりにあるもの、人びとの顔、鏡に映った自分の姿、目に入る風景、雲や木々の形、天候の変化、鳥の飛翔、昆虫の足跡にさえ意味を見出そうとする。世界でもとくに古い書記法である楔形文字は、五千年前にユーフラテス川の泥についた雀の足跡を模してつくられたという伝説がある。私たちの祖先は、それを偶然についた痕跡とは思わず、神意を伝える謎めいた文字だと考えたのだ。」(P244)
人は意味に飢えている。
「…ヴォルテールはパスカルに異論を唱え、さらにこうつづけた。「心を慰めるためには、蜘蛛と土星の環のあいだにどんな関係があるのかなど知らないほうがよい。自分の手の届く範囲のことだけを追求すべきである。」」(P247)
私も、抽象的な問題をどう考えても、結局は自分の手の届く範囲のことしか、触れることも感じることも、また何か影響や変化を及ぼすこともない、自分の力の限界を冷徹に考えたことがありました。
「野生のままの自然とは、いわば閉ざされたままの本である。ページを開いて読みはじめなければ、中身は存在しない。」(PP251-252)
「…オルダス・ハクスリーは『知覚の扉』に書いている。「だが、いかなる状況にあっても、常に孤独である。殉教者は手に手をとって刑場に歩み入るが、十字架にかけられるときは一人である。抱き合う恋人たちはそれぞれの恍惚を溶けあわせ、自己を超越したひとつの存在に昇華しようとするが、それはむなしい試みだ。そもそも、人間の形をとった魂はすべて、苦しみも喜びも孤独のうちに味わうものである。」」(P258)
これは個人の知覚について書かれているなら、オクタビオ・パスが『弓と竪琴』で真理の感得について語ったことに等しい。
「アレクサンドリアの図書館の目録作成に苦労した担当者がいうように、二つの写本は決して同じものにはならず、「決定版」を選ばなければならなかった。」(P290)
本は、複製という同義反復のままに止まって制限され続ければいいが、「読者はそれぞれ、自分の本に書き込みをし、しみをつけ、さまざまな痕跡を残して、自分だけの一冊を作り出す。そうなると、一度でも読まれた本は、もはやけっして他と同じにものにならない。」(P290)一つの物語から、「さまざまに形を変えた物語が派生した。」(P394)オリジナルの本とは、引用とは無縁なのか。「一冊の本は過去のすべての本の血筋を受けついでいるからだ。」(P396)
「すべての読者が知っているとおり、本を読むという行為の要点、すなわちその本質はいまも、そしていつまでも、予測可能な結末がないこと、結論がないということだ。読書のたびに、それは別の読書へとつながる。」(P294)
さらに次回で。
伊豆の温泉に入った [ガン闘病記]
 7月にしては最強の台風8号が関東直撃という7/10に、伊豆に保養を兼ねて家族で乗り込みました。
7月にしては最強の台風8号が関東直撃という7/10に、伊豆に保養を兼ねて家族で乗り込みました。
やはり、旅館ではキャンセルも多かったらしく、梅雨の最中とはいえ空いてました。
さいわい雨に降られることもなく傘もささずに目的地へ。
娘が、事前に親孝行と手術の快気祝いということを伝えていたせいか、旅館では心のこもったおもてなしを受けました。また、料理もおいしく、懐石コースで伊勢海老やアマダイの刺身やら、牛のステーキなど…、食の細っている食欲でしたが、有難いやらもったいないやらで一生懸命に食べて満腹。旅から戻ったら1キロ太ってました。これが維持されて、体力を早く戻したい。
まだ9時でしたが、食後部屋に戻って横になったら、旅の疲れもあり、そのまま朝まで寝てしまいました。夜間も多少雨はあったかもしれませんが、暴風雨という感じは何もなかっようです。
予想通り、翌日11日は台風一過の上天気。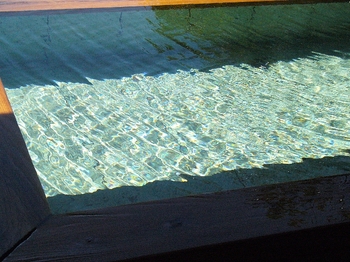 水平線にうっすら伊豆大島を確認することが出来ました。
水平線にうっすら伊豆大島を確認することが出来ました。
朝に露天で一風呂浴びて、坂道を歩くと息切れしてしまうので、少し観光もしながら帰路へ。
いい旅を用意してくれた子供に感謝した一泊の旅でした。
アルベルト・マングェル『読書礼賛』(1) [本]
この400ページを超える本を一つの読書メモに仕上げることは無謀な試みだと思う。特に、訳者あとがきにもあるように、
「初出一覧を見ると、執筆時期は古くて一九九八年、最新のものは二〇〇九年である。テーマは多岐にわたり、人種問題、ジェンダー、創造的な贋作について、社会的責任と文学の役割、テクノロジーと書物といった大きなテーマを扱うかと思うと、編集者、翻訳者、出版人の役割を具体的に論じたものもある。
広範な話題にもかかわらず、この本を通して読むと、はからずも時間を追って著者の半生をたどることになる。」(P426)
訳者の野中邦子がいうとおり、読書についてのエッセーというよりは、読書をふくむ半生のメモワールという印象があります。共感できる言葉も多く、重いテーマ(例えば自身がユダヤ人であること)も多数含んでいて、さらっとながしてはいけない本だろうと思います。前著『図書館 愛書家の楽園』は読んだもののまだ取り上げていませんが、この『読書礼賛』を丁寧に記しておきたいと思います。
「人は世界に足を踏み入れたとたん、あらゆるものに物語を見出そうとする。風景、空、他人の顔、そしていうまでもなくわれわれ自身が生みだしたイメージと言葉のなかに物語を見出す。」(P9)
「…私たちがこうあるべきだと信じる本の姿は読むたびに変わる。長年のうちに、私の経験、趣味、先入観は変化してきた。…「万物は流転する」というヘラクレイトスの名言は、私の読書にもあてはまる。「同じ本を二度同じように読むことは出来ない」」(P10)「G.K.チェスタトンはあるエッセイでこう述べている「どんな本でも、一冊の本がそのためだけに書かれたと思わせるいくつかの言葉がある」。」(P39)
この言葉は、著者の意図を直感的に感じるものがある、ということなのでしょう。
大池文雄『水戸コミュニストの系譜』で、「安東仁兵衛の「戦後日本共産党私記」を読んで、もしかしたらこの本は査問・リンチ事件の、この一章を書くために書かれたのではなかったか、そこに隠されたキーがある、と私は思った。…しかしこの本はその目的を達しただろうか。ひとをも自分をも傷つけないように用心深く書かれた綴り方。この懺悔は果たして彼に解脱を齎しただろうか。」(P54)
「論文とりわけ博士論文というのはなんと奇妙な形式だろう。…重要なことは数行で書けるのに、そのために数百ページを要し、しかも各章に数十の注を付す。権威主義の典型だろう。…もし真の反抗が起こるとすれば、それはアカデミズムの作法に精通し、その矛盾と空しさを徹底して味わった人たちの間からではないだろうか。」とは、西川長夫の『植民地主義の時代を生きて』のあとがき(P580)。
「…学者たちの書くものはどうしてあんなに分厚いのですかねえ?いうことがあまりない時、人々は無理やりことばを積み上げようとするからながくなるんじゃないかしら?私の考えでは、人間に関する思想で二百語以内で表現できないことなんてそんなにないと思うんですが、あなたはどう思いますか?」とはエリック・ホッファー『百姓哲学者の反知識人宣言』のことば。
本は、人のためというよりも前に、まず《商品》にならなければ、本になることすらないのでしょうか?
マングェルは違う箇所で、フローベールの言葉として「長い本はいつも真ん中あたりのページでうんざりしてしまう」(P190)と紹介しています。
「…どれほど勤勉に努力しても、目的が高尚でも、よき相談相手がいても、水ももらさぬ調査ができても、痛ましい経験があっても、古典の教養があっても、音楽を聴く耳があっても、文体の趣味がよくても、良い文章がかけるとはかぎらない「ペンはない、インクもない、テーブルもない、部屋もない、時間もない、静けさもない、やる気もない。」とジェイムス・ジョイスは一九〇六年十二月七日、弟に宛てて書いている。まさにそのとおりだ。」(PP40-41)
『ユダヤ人であること』では「私はユダヤ人なのか?私は何者なのか?」(P47)とアイデンティティの危機がにじみ出る文章。
「どんなジャンルも成立と同時に前史が生まれる」(P53)
「ジュネは、抑圧者には絶対に譲歩してはならないということを肝に銘じていた。」(P56)
「ジャン・コクトーがジュネの『花のノートルダム』の原稿をポール・ヴァレリーに見せようとしたとき、ヴァレリーは「そんなものは燃やしてしまえ」といった」(P57)
「ブエノスアイレスの高校を卒業してから、…パリとロンドンですばらしい十年を過ごした。…図書館では…暇つぶしのために何冊か本を借り、最後まで読みとおすことはまれだった。方針もなく、知識にもとづいた秩序もなく、義務感もなく、厳密な探究心もない。それが私の読書体験だった。体と同じく、心もさまよっていた。」(PP65-66)
「一九七〇年十一月、私が穏健なるアナキストになったのはこういうわけである。」(P71)
第1章「私は誰?」をしめくくる『プロメテウス頌』は2ページほど、短いながら「その問題は古代からのものだ、と私の書斎が教えている。」(P72)と書き始められ、マングェルの問題意識を要約している重要な文章です。
第2章「巨匠に学ぶ」は、ボルヘスについてのエッセイがまとめられています。
「若いころボルシェビキ革命賛美の詩を書いたことに後悔の念を抱いていたボルヘスにとって、共産主義は憎悪の的だった。」(P79)
「ペロン政権下のアルゼンチンで、ナチに反対する意見をはっきりと述べた数少ない知識人のひとりがホルへ・ルイス・ボルヘスだった。」(P101)「彼は政治を嫌い(「人類の行為の中で最も悪辣だ」)フィクションの真実を信じ、真実の物語を伝えようとする人間の能力を信じたのだ。」(P104)
ボルヘスの作品の魅力を伝える文章がありますが、これらは読んでいただきましょう。
第3章「覚え書」で、チェ・ゲバラを評し、「チェは私たちが見たのと同じものを見た。私たちが感じたのと同じことを感じた。「人間の境遇」が根本的に不公平であることに怒りを覚えた。だが、私たちとちがって、彼はそれをなんとかしようとして行動した。」(P127)その結果については、疑問を記しています。
「ドン・キホーテがいうように、不正行為のほとんどは、責任をとるべき人びとが結果を引き受けずにすむとわかっているからなされるのだ。」(P156)
「隠喩は隠喩の上に、引用は引用の上の築かれる。人によっては、他人の言葉を引用の源泉と見なし、それによって自分の考えを表現する。また別の人びとにとっては、他者による言葉が自分の考えそのそものであり、他人が考え出した言葉を形だけ変えて紙の上に並べ、語調や前後の脈絡を変えることで、まったく別のものにつくりなおす。このような連続性、このような盗用、このような翻訳作業がなければ、文学は成立しない。そして、このような作業を通して、文学は永遠性を保つ。周囲の世界数変化するなかで、飽きもせずに寄せては反す波のように。」(PP168-169)
このことを、第2章でボルヘスが愛読したサー・トマス・ブラウンのことばを紹介していました。
「どんな人も、その人だけの存在ではない。これまで大勢のディオゲネスが生きてきたし、同じぐらい大勢のティモンがいたが、名前が残るのはごく少数である。人は何度も生きなおす。いまの世界は、過ぎ去った時代の世界と同じだ。過去に同じ人間がいたわけではないが、同じような人間はつねに存在した。その人間の本質はいまも昔も変わらず、何度もよみがえる。」(P92)
後半は、次回にしましょう。
「パストラル-牧歌の源流と展開-」 [本]
牧歌を題材に、文学、美術、音楽、演劇などの芸術史に8人の研究者の方々が論じていて、私は教えられこともたくさんあり、面白く読めました。
書店でこの本を見つけて、ぱらっと見た序章で、ニコラ・プッサンの『アルカディアの牧人たち』の画が取り上げられていたので、すっと引き込まれました。
第一章で、テオクリトス(前三世紀)が、牧歌の始祖として位置づけられる、としています。
「テオクリトスはシチリア出身であるが、後にアレクサンドリアに移住している。・・・テオクリトスが活躍したヘレニズム時代では、大都市の発展に伴い、田園は都市住民の生活空間から離れていった。これは、前四世紀前半までの古典時代において、ポリスと農民が密接につながっていたことと、大きく異なっている。その結果ヘレニズム時代においては「田園を理想化し、自然に囲まれた生活に郷愁を見出す牧歌という文学」が成立することになったのである。」
「テオクリトスの『牧歌』はドリス方言で書かれ、田舎びた言葉、素朴な響きで牧人の雰囲気を伝える。」(P25)
と簡潔に牧歌を説明されています。
糸杉と死の関連について、オデュッセイアを紹介する中でなるほどとうなづける安村典子氏の文章がありました。
「(カリュプソ)島中に漂う香り、繁茂する糸杉、スミレの花などは、特殊な意味を持っていると考えることができる。これらが「死」を象徴するものとして理解しうることは、すでに拙論で述べている・・・一例を挙げれば、古代ギリシアでは、糸杉はその芳香ゆえに、死者を火葬する際の薪として重用されていた。糸杉の薪を十分に調達できない場合は、さまざまな木で作られた薪を積み上げた上に、葬いであることを示すために、象徴的に糸杉の一枝を載せる習慣もあった。」(P30)
といいます。
テオクリトスがギリシア古典時代にシチリアのシュラクサイを理想郷として描いたが、ローマ時代になりシチリアを属州としたことによって大きな変化が生まれた。ウェルギリウスは、シチリアではなく牧人の神であるパーンの故郷とされるアルカディアが選ばれる。そこはギリシアのペロポネソス半島中央部の、現実のアルカディアとは異なるといいます。
それから、旧約聖書、古代エジプトの愛の歌、雅歌などに、パストラルを各論者が読み解きます。
とくに、河島思朗氏がウェルギリウスでの《祖国》、さらに川島重成氏がウェルギリウスの歴史観に注目して聖書的歴史観(予型論的歴史観)と対比します。
英国文学におけるパストラル思想(第六章)。ユートピア、森のラテン語と英語の違いなど踏み込んだ検討、エコロジーの思想まで展開するのも面白い。イギリス、パストラル風ロマンス劇としてシェイクスピア『お気に召すまま』をとりあげています。その中で、皮肉屋「ジェイキスにとって、人生は舞台でそれぞれの時代を演じる役者であり、人の一生は無に過ぎない」(P207)という見方と、老僕アダムによるジェイキス批判というテーマを取り上げています。しかし、ジェイキスの台詞は「人とは何か?人とは何でないのか?影の見る夢―それが人間なのだ。」というピンダロスの『祝勝歌』や、ボルヘスがテーマにしたことと通じるところが感じられます。老僕アダムがどう批判するのか、シェイクスピア『お気に召すまま』を読んでみようか、と思いました。
つづいてミルトンとパストラルの伝統(第七章)、最後が金澤正剛氏による音楽におけるパストラル。
「ヨーロッパ音楽史にパストラルが始めて登場するのは、十二、十三世紀フランスの中世歌人の田園詩、ないしは牧歌としてである。これらの歌人には二つのグループがあり、先に活動したのトゥルバドゥールの活動地域はフランス中部から南部にかけてで、オク語と呼ばれる古語を用いて詩を書いていた。また彼らよりも半世紀遅れた活動を開始したトルヴェールたちは来たフランスで、フランス語のルーツともいえるオイル語による詩を書いていた。」(P241)
従来、トゥルバドゥールたちが放浪の吟遊詩人と見なされてきたが、それは違う、と指摘(P241)されています。
中世歌曲、ルネサンス後期の牧歌劇、とくに『エルサレムの解放』を書いたタッソーによる牧歌劇『アミンタ』の成功が人気の口火といいます(P252)。それを受けてグァッリーニの牧歌劇『忠実な羊飼い』が書かれたとのことです。
それから、クラシック音楽にパストラルを取り上げ紹介しています。有名な『グリーン・スリーブス(緑の袖)』もまた、もともとはパストゥーレルの主題を受け継いだもの(P251)と指摘されていました。
ただ一点だけ、「さらにヴィヴァルディは一七三七年ごろに管楽器による合奏曲を作品一三として出版したが、それに『忠実な羊飼い』という題をつけたのも、管楽器がもともと羊飼いの楽器であるということと同時に、グァッリーニの牧歌劇にあやかろうと考えたのは明らかであろう」(P257)。この作品は、長くヴィヴァルディの作品と信じられてきたが、1974年に音楽学者から疑義が発せられ、1989年にニコラ・シュドヴィル(1705-1782)の作品であることが突き止められています。これは訂正しておきたいです。
ついでにもうひとつ校正の問題でしょうが、214ページの冒頭行が、前のページのアイリアノス『奇談集』の引用と連続しておらず、ピケナス出版の方がご覧になっていたら、これも正誤表があれば欲しい所です。
さて、バロック音楽以降のパストラルは、ドビュッシーの『牧神の午後の前奏曲』、「パンの笛、またはシランクス」などもあり、読みながら、音楽の魅力が呼び起こされました。私が持っているCDからも紹介しておきましょう。
P.O.フェルー「フルートのための3つの小品 Ⅰ.恋する羊飼い」
ポール・タファネル「アンダンテ・パストラールとスケルツェッティーノ」
ボザ「夏山の一日 1.パストラール」
メンデルソーン「無言歌 5.羊飼いの訴え」
グリーク「抒情小曲5-1 羊飼いの少年」
他にも、ドヴォルザーク「チェコ組曲 前奏曲(パストラール)」シベリウス「ぺリアスとメリザンド 5.パストラール」などまだまだあるようです。
トゥルバトゥールについては、早川書房のナショナル ジオグラフィック・デレクションズのW.S.マーウィン『吟遊詩人たちの南フランス』、もっと古くは筑摩叢書198のアンリ・ダヴァソン『トゥルバトゥール 幻想の愛』という書物があることを知っています。田舎での郷愁を誘う幼い恋愛だったり、つれなく満たされない片思いだったりする詩情が、私には魅力です。しかし、それだけに止まらず、差別された南仏、都市に対立する“後進化”された地方、という意味で、オク語や異端カタリ派の歴史にも興味があります。シモーヌ・ヴェイユが『オク語文明の霊感は何にあるか?』を書いたことに注目してもいます。
そんな訳で、すごく刺激を受けた本でした。
ガンの宣告と読書(時間)などについて [ガン闘病記]
ガンの宣告を受けたときは、昨年に家内の叔母が、やはり末期の肺がんで、発見から半年でなくなったため、もしかしたら自分も短命で、この蔵書の全部は読みきれないのか、と愕然とした気分になりました。読む時間があるとすればどの本を読むか? 根拠があって選ぶことの出来た本は結局なかった、と告白します。いや読むことより、自分なりに何か書き記すことが大切ではないか? また、クラシック音楽も改めて聴く時間がどれだけあるのか? モノとして持っていることとそこに向き合える自分の使える時間を深刻に考えました。天秤にかけるというよりもたどり着けず、引き離される感覚です。寓意絵画にみる書物とドクロ、「死を思え」という教訓そのままの感覚です。
術前に肺の切除のため、肺活量が25%ほど落ちると言われていたことですが、実際には、手術をして1ヶ月たちますが、術前の肺活量からすると50%程度しか回復しておらず、酸欠気味。鎮痛剤の影響もあるのでしょうが、貧血症状のように頭がボーっとしてしまい、集中力が続かない。腹式呼吸で酸素の取り込みを増やすべきなのは判っているのですが、痛みのせいか肺だけの浅い呼吸になりがちなので、どうしてもハァハァしてしまう。気づいて深呼吸しても、既に体が酸欠になっているため、一度横になって軽い睡眠をとり、体の酸素消費量を押さえ、脳に酸素が回るようにしないと、ボーっとした状態を回復できない。
仕事を休んでたっぷりと時間があるのに、活動の非効率は避けられないのが惜しい。
まぁ、あせらずもっと生きている時間を素直に楽しみたいとも思います。
娘が来週に伊豆の温泉を手配してくれて、湯治をかねて家族でゆっくり旅に出かけることを、楽しみしています。
中神美砂『令嬢たちの知的生活-十八世紀ロシアの出版と読書』 [本]
このユーラシア・ブックレットは、気になるテーマを取り上げているので、ついつい気にかけてしまい、これまでも何冊か購入しました。
アルメニア近現代史-民族自決の果てに
ロシア史異聞
十九世紀ロシアと作家ガルシン-暗殺とテロルのあとで
アレンスキー-忘れられた天才作曲家
スターリンの赤軍粛清

令嬢たちの知的生活―十八世紀ロシアの出版と読書 (ユーラシアブックレット)
- 作者: 中神 美砂
- 出版社/メーカー: 東洋書店
- 発売日: 2013/05
- メディア: 単行本
今回は、令嬢たちの知的生活。
「ピョートル一世が実施した一連の近代化・西欧化政策の中で、ロシア女性の立場に大きな影響を与えた三つの政策がある。」(P7)として、第一に女性の相続・財産権を持てるようにした。
「18世紀において女性が財産権を持っていたのは、西欧諸国の中ではロシアだけだった。」(P8)
第二に公式の祝宴や夜会への夫人及び娘の同伴命令。
第三に女性が教育を受けることが出来るようにした。
十八世紀後半の教養女性の代表ダーシコワは、回想録で「十九歳の結婚当時、私は九百冊の蔵書を持っていました」という。「印刷された書籍の価格は高く、購入できたのは裕福な上流貴族などに限られていた。書籍一冊の平均価格が1ルーブルで、この金額は一ヶ月の労働者を雇うのに十分な金額だった」と文化史家クラスノバーエフは語る。
ダーシコワの死後、蔵書カタログによると、フランス語書籍1650冊、ロシア語書籍1353冊、英語書籍520冊、ラテン語書籍453冊などで、雑誌を加えると総数は4500冊以上に及んでいる(P26)、ということです。素晴らしい。
在ロシア・フランス大使のセギュール伯爵は、1780年代のペテルブルグの貴族社会の女性について、「女性は向上の道において男性よりずっと先を進んでいます。上流社会において出会った多くの夫人や子女は美しく着飾るだけでなく、四つか五つの言語を話し、しかも様々な楽器を演奏でき、フランス、イタリア、イギリスの有名な作家の作品を読んで知っています。」と教養の高さを評価しています。(P34)
教養ある女主人を中心にした社交形態のサロンについて紹介されています。(P48)
こうしたサロンが、進歩的な青年貴族の反乱(デカブリストの乱)のように体制と対立することがあっようです。
このデカブリストの反乱について言及している本がありました。田中克彦『シベリアに独立を!』で、1825年、
「首都ペテルブルグの元老院広場で若い貴族の子弟たちを含む知識人たちが専制と農奴制の廃止を求めて立ち上がった。蜂起は簡単に鎮圧され五人の首謀者が絞首刑を執行され、121人がシベリアに送られた。・・・夫だけをシベリアにやらせるわけにはいかないというので、若い妻たちの知られているだけでも11人もが貴族の身分を捨てて夫を追ってシベリアに向かうことを願い出て許され、それぞれ運命をともにした。再び首都に戻ることなくシベリアの流刑地で果てた・・・」(P4)
「十九世紀中頃、最も人気のあった詩人ネクラーソフの、夫を追いかけて、中にはフォンヴィージナ夫人のように二人の幼児を置いて、困苦の待つシベリアへ向かった・・・皇帝は妻たちがシベリアに行くことによって生ずる社会的動揺を恐れて、道中要所の役人たちに命じて何とか思いとどまらせようとするが、妻たちは役人に向かってこう答える。
たとえ死ぬさだめであろうとも
少しも悔いはございません・・・
わたしはまいります! まいります! わたしは
夫のそばで死なねばなりません。(『デカブリストの妻』岩波文庫P54-55)」(P6)
「ペテルブルグで最も機知に富んだ、学問の香り高いサロンはカラムジナーのサロンである。・・・ペテルブルグに住む有名人や才能豊かな人は毎晩カラムジナーのサロンを訪れた。心温まるもてなしであったが、非常に簡素だった。」(P56)
「彼女のサロンの常連は、作家ジュコフスキー、プーシキン、レールモントフ、ホミャコフ、ツルゲーネフだった。彼女のサロンは通常十時に始まり、夜中の一時、二時まで続いた。平日は八人から十人ほどが集まり、日曜日にはより多くの人が集まった。サロンは地味で、赤い毛織物で覆われた家具があった客間で、出されたものは、とても質素で、濃いお茶と濃厚なミルクと、バターがついたパンだけだったとされる。しかし、このサロンは誰からも愛されていた。」「カラムジナーのサロンから出てきた人たちはまるで生き返ったように、生き生きしている」「カラムジナーのサロンでは話のテーマは哲学的な問題ではなかったし、ペテルブルグのつまらない噂でもなかった。ロシア文学と外国文学、そして我が国とヨーロッパの重要な出来事が話の話題だった。・・・私たちの心と耳を生き返らせ、豊かにしてくれた。それは当時の息苦しいペテルブルグの雰囲気の中では特に有益だった。」と、暖かく、愛らしい、高い倫理観のある家としている。(P57)

![禁断の惑星 [DVD] 禁断の惑星 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21KA1XEP4ZL._SL160_.jpg)







